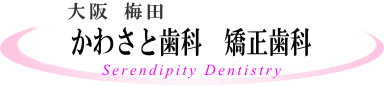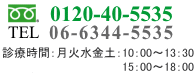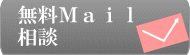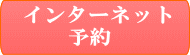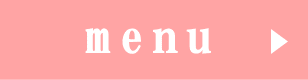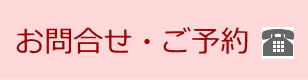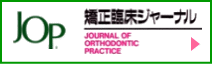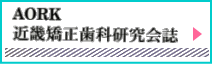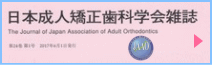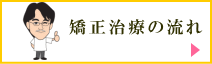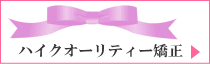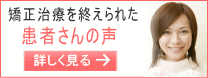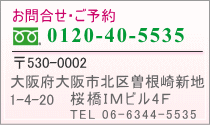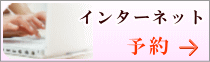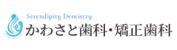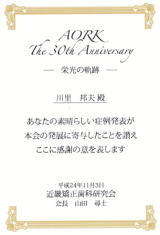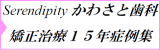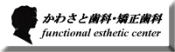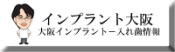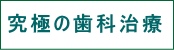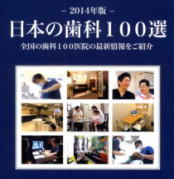医院設備のご紹介
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
セレック3D
セレックはレーザー光線で写真を撮り、パソコンでデザインをして作ります。従来のようなお口の中で形をとる煩わしさがありません。

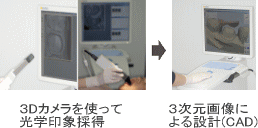 |
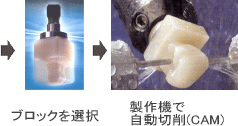 |
マイクロスコープ
ルーペ&マイクロスコープで最先端の歯科医療
歯科診療はミクロの世界を扱う繊細な作業の連続です。
この細かい作業は今まで肉眼で、時には手探りで行われていたため、その精度には限界がありました。
当院では、脳外科手術などで使用されている拡大鏡(ルーペ)や実体顕微鏡(マイクロスコープ)を用いて、ミクロの世界を 拡大下 で処置することにより、精度の高い歯科医療を皆様に提供します。
そのため、肉眼では捉えにくい部位を正確に確認、把握できることが侵襲を低く押さえ、精度の高い治療が再治療の発生率を低くします。
|
人間は裸眼での二点識別閾は、0.2 mm程度と言われています 。
歯科治療において、たとえばクラウンの適合性は数十 um 程度であれば良好とされていますが、このレベルは0.2 mm をはるかに下回ることになります。また、歯肉を剥離して直視下で歯根を観察した場合、根面にスケーラー等でできた傷なども裸眼では見逃されることになってしまい、滑沢な根面を得ることができなくなる可能性も否定できません。
すなわち、 裸眼による治療では、術野に何が見えているかを十分に把握しうるものではなく、おのずとその限界があります 。
拡大率に関しては、必ずしも高倍率を使用すればそれでよいというものではなく、診査、術式などにより、臨床的に有効な倍率は異なるものと考えられます。たとえば、診査(クラウンマージンの適合性、根の破折、副根管の探知など)やマージンフィニッシュなどでは10~20倍程度、圧排やグロスプレパレーションでは3~10倍前後といったように、各臨床ステップで有効な倍率がことなるものと考えられています。そのため、1つの倍率のルーペのみでは、その対応におのずと限界が生じるのです。
マイクロスコープの歴史としては、1950年代に耳鼻咽喉科で始まった顕微鏡下での微少組織に対する治療は従来直視下で行われてきた分野において革命的に治療の質を高めるのに貢献してきました。使われる目的は多岐に渡っており、生死を分けるような脳外科手術から失明防止などの疾患による人体機能停止を防ぐ手術、整形、形成分野での機能や形態修復を目的とした手術、聴力、視力の改善といったより QOL の向上のための手術等、医学での微少組織への顕微鏡手術は当然のこととして実施されています。
歯科における顕微鏡治療は、国内においては1990年代後半より次第に実施されつつあります。これは、1990年初頭よりアメリカの歯内治療の卒後研修では顕微鏡治療が必修科目となり、一般歯科医においても顕微鏡治療のメリットが認める所となったことが背景にあります。医学での歴史を見れば分かる通り、今後治療の質向上とそれに伴う患者サービス、他医療施設との差別化を考えれば一般歯科医への普及は目前まで迫っているといえます。
顕微鏡治療のメリット(手探りの治療から観る治療へ)
明るい 照明下 で 拡大 して治療が行えることが第一に挙げられます。
額帯式ルーペという手もありますが、術者の頭の移動と同時に観察野が移動してしまう点や倍率が固定で充分な作動空間が得られないという点がデメリットです。根管治療では、肉眼では捉えきれなかった第3、第4の根管や lsthmus の発見が治療成績の向上をもたらし、術後感染が著しく低下し患者からの高い信頼を得ることが出来ます。
また、穿孔部の閉塞は顕微鏡によりかなり深部まで確認することが出来るので非外科的な治療が可能となります。根管内器具破折では充分な明るい視野を確保することにより歯質の除去を最小限にとどめて正確に処置することが出来るようになります。手術においては、拡大することにより切開面積を最小限にとどめて感染や術後の痛みといったリスクを最小限に押さえます。
補綴では、マイクロメーターのオーダーで精巧に造られたクラウンやブリッチのフィッティングに威力を発揮します。その他、歯周病治療ではポケット測定や歯石の発見、確認を最大視野で行えることが治療成績の向上をもたらします。
ルーペと違い、顕微鏡には付属品が付くというメリットもあります。
写真機やビデオを取り付けることにより患者への説明がビジュアル化でき、インフォームドコンセントに役立ちます。
クイント新聞掲載記事
癒しの時代 歯科医院の設計・デザインは 原 兆英
 |
クリニックのリニューアルで、予防型歯科医院経営を志向する
「予防歯科」とデザインとの関わりは?
ここ数年、北欧ブームが続いている。優しい表情をもつ文化や製造への共感があるのだろう。日本にもかつては北欧と同じような空間の設えや工夫(茶室や雪見障子など)があった。そうした日本人の遺伝子が、北欧のインテリアやファブリックなどの、シンプルで洗練された美しさ、兼ね備えた「こだわり」や「工夫」といった機能に惹かれるのだ。スウェーデンの家具メーカー・IKEAやフィンランドを舞台にした日本映画「かもめ食堂」が、女性たちのあいだで人気を博しているのも理解できる。わかりやすく優しいデザインは、ブームに留まらずに、これからも長く指示されるだろう。
では、こうした傾向がクリニックの空間デザインにも当てはまるのか?答えは2割がNo、8割はYes。これは、虫歯や歯周病の治療よりも、疾病予防や審美治療の割合が逆転するという、今後の歯科の変化を予測するときに直感できる割合だ。現に、予防歯科先進国のスウェーデンでは、定期険診受診 率が成人の80%超、子どもは100%近くに及ぶという。10%未満の日本ですら、ここ10数年で子どものう蝕罹患率は半減しているそうだ。
遠からず「治療」と「予防」の比率が逆転するという前提で、空間デザインの話に戻ろう。前途のように予防や審美が主な診療科目になれば、クリニックの利用者は健康な人たちが多くなる。プチ整形という前例もあるように、彼女たち(彼たち)はまるでブティックやエステサロンに行くような気軽さでクリニックを訪れる。歯科空間のデザインも、多くの健康な人に指示されるべきだと私は考える。
今年、弊社が曽根崎新地(大阪)で手がけたデザインに、ビル内に移転後、開院したクリニックの例がある。現地調査の際に、隣接施設が美容整形外科であることがわかった。経営戦略的に考えれば審美治療の顧客と重複する患者の獲得が見込め、自由診療の対象としても見逃すことはできない。つまり、前項にあるように治療以外の利用者を取り込む空間デザインの好例となったのである。デザインは「わかりやすく優しい表情の空間」を心がけ、オフホワイトを基調としたカラーリングに、アクセントとして北欧イメージの青など数色を使用した。インテリアは、スカンジナビアから輸入した木製のシンプルな家具や小物。キャビネットの中に飾った本や置物、そしてレセプションと診療スペースを区切るガラスに掛けたファブリックも同様のテイストでそろえた。いずれも本物がもつ質感が優しい表情を醸し出し、節度あるモダンさがクリニックに清潔感や安心感を生み出した。
これまで2回にわたってご紹介したように、空間デザインは、ポリシーや立地などを含めて総合的に空間価値を高める必要がある。先に述べたクリニックは、予測通り新規顧客や女性利用者からも好評だそうだ。健康な人が利用者の核となるという考えは、これからのクリニック経営に重要な意味をもつ。ぜひ歯科医師の皆さんにも、一歩先を読んだ空間づくりに活かしてもらいたいと願っている。
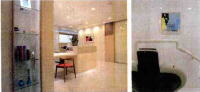 |
|
| かわさと歯科(大阪・曽根崎新地、川里邦夫院長)かわさと歯科の診療室 |
原 兆英 profile
東京に生まれる。ジョイントセンター㈱代表取締役
日本インテリアデザイン賞・商空間デザイン賞優秀賞・ディスプレイ産業大賞優秀賞・商環境デザイン賞優秀賞、2002年、2005年グッドデザイン賞、その他多数受賞。
|
お問合せ・ご予約 06-6344-5535 |
|